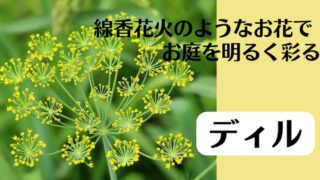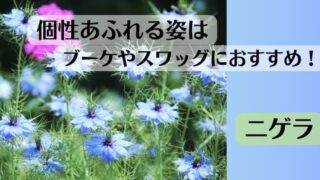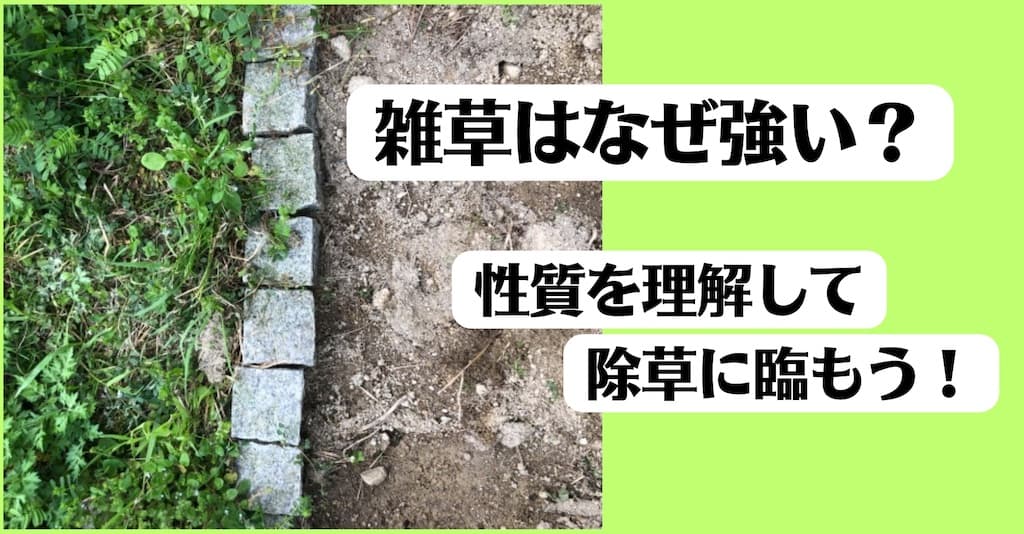はじめに

「ハーブの植え替えをしたら、急に元気がなくなってしまった…」そんな経験はありませんか?
庭づくりや鉢植えの管理をしていると、株の移動や植え替えはよくある作業ですが、実は、植え替えを苦手とするハーブがあるのをご存じでしょうか?これを知らずに育ててしまうと、気づかないうちにハーブが弱ってしまうこともあります。
そこで今回の記事では、植え替えが苦手なハーブの品種やその理由、さらに枯らさないための育て方や対策を詳しく解説します。ハーブを健康に育てたい方は、ぜひ最後までお読みください!
移植を苦手とする主なハーブ
フェンネル

フェンネルの特徴や育て方は下記のページにて。
ナスタチウム

ナスタチウムの特徴や育て方は下記のページにて。
カレンデュラ

コーンフラワー

コーンフラワーの特徴や育て方は下記のページにて。
ディル

ディルの特徴や育て方は下記のページにて。
ボリジ

ニゲラ

ニゲラの特徴や育て方は下記のページにて。
イタリアンパセリ

イタリアンパセリの特徴や育て方は下記のページにて。
移植を嫌う理由
これらのハーブが移植を苦手とする最大の理由は、「直根性植物」であることにあります。
直根性植物とは、根が真下にまっすぐ伸びる性質を持った植物のことです。

大根やゴボウが代表的な例で、これらの植物は一本の太い根(主根)を持ち、それが深く地中に伸びていきます。一方で、細かい枝分かれの根(側根)はほとんど発達せず、あってもひげのように細い程度です。
対照的に、地表近くに広がる浅い根を持つ植物は「浅根性(せんこんせい)」または「ひげ根」と呼ばれます。直根性植物にとって、太い主根は生命線そのもの。この根が傷ついたり切断されたりすると、植物の生育に深刻なダメージを与えてしまいます。
そのため、掘り起こして根を傷つけるリスクのある「植え替え」は、直根性植物にとって非常に負担が大きい作業といえるのです。
直根性植物を育てるときの注意点
直根性植物を育てるうえで最も大切なのは、「根にできるだけ負担をかけないこと」です。根が傷つくと生育に深刻な影響を与えるため、特に移植には注意が必要です。
直まきで育てる方法
直根性植物は「直まき」で育てるのが理想的です。種を栽培する場所(鉢、プランター、または庭)に直接播き、間引きながら成長させましょう。この方法なら、根を傷つける心配がありません。

- 種まきのポイント
種を播く際は、間引きが不要になる程度の十分な間隔を空けて播くのがおすすめです。もし間引きが必要な場合でも、隣接する苗の根を傷つけないよう慎重に作業を行いましょう。
ポット苗の場合
ポット苗を使用する場合や、発芽後にポットに移植した苗を育てる場合には、どうしても移植が必要になります。その際には、以下の点に注意してください。
- 根鉢を崩さない
ポット苗を取り出すとき、根と土が一体化した「根鉢(※)」を崩さないように気をつけましょう。根鉢が保たれていれば、根へのダメージを最小限に抑えることができます。 - やさしく植え付ける
移植の際は、根鉢をそっと扱い、苗を新しい場所にやさしく植え付けます。土は苗をしっかり支えつつ、根を圧迫しない程度に固めましょう。
一年草の特性を活かす
今回ご紹介した直根性ハーブ(例:ディル、フェンネルなど)は一年草です。そのため、栽培する場所に直接種を播き、一度の育成で完結させるのが理想的です。植え替えの必要がない栽培計画を立てることで、ハーブを元気に育てられます。
育苗する場合は、根にダメージを与えずに定植できる「紙製ポット」がおすすめです。下記のページで詳しく解説しておりますので、あわせてご覧ください。
直根性ハーブにおすすめの紙製ポット↓↓
ハーブ以外の直根性植物
ハーブだけでなく、直根性を持つ草花や野菜も数多く存在します。ここでは代表的な例をリストアップしましたので、ハーブ以外を育てている方もぜひ参考にしてみてください。
<直根性の草花(例)>
・朝顔
・アスター
・イベリス
・オダマキ
・オルレア
・カスミソウ
・クレマチス
・ケイトウ
・シノグロッサム
・スイートピー
・スターチス
・ニチニチソウ
・ネモフィラ
・ヒヤシンス
・フウセンカズラ
・ポピー
・ルリタマアザミ etc
<直根性の野菜(例)>
・枝豆
・エンドウ
・オクラ
・カブ
・ゴボウ
・ソラマメ
・ダイコン
・トウモロコシ
・ニラ
・ニンジン
・ホウレンソウ etc
これらの植物もハーブ同様、移植を嫌う性質があります。そのため、種まきや栽培時には根を傷つけない工夫をすることが大切です。特に直まきや適切な間隔での播種を心がけると、健やかな生育をサポートできます。
最後に
今回は、植え替えを苦手とする直根性のハーブについて詳しくご紹介しました。
「すでに育てているけれど、こんな特徴があるとは知らなかった!」という方や、「これから育ててみたい!」と思った方にとって、この記事が少しでも参考になれば幸いです。
もし、まだ種まきが済んでいない場合や、育て方についてさらに知りたい方は、ぜひ以下のページもチェックしてみてください。