はじめに
「ハーブを育てたいけれど、土づくりってどうすればいいの?」と悩んでいませんか?
この記事では、ハーブ栽培に適した土壌改良材の選び方と使い方を初心者向けにわかりやすく解説します。
土の基本的な性質や配合については、以下の記事で詳しく紹介していますので、まずはこちらをチェックしてみてください。
そして今回は、ハーブの成長をさらに後押しするために欠かせない「土壌改良材」に焦点を当てて解説していきます。
「市販の培養土から卒業して、自分だけの理想の土を作りたい!」
「庭の土が固すぎたり、水はけが悪くてハーブがうまく育たない…」
そんな方に向けて、土壌改良材の基本と活用術をわかりやすくお伝えします! ぜひ最後までご覧ください。
土壌改良材とは?
土壌改良材とは、土に混ぜることで植物が育ちやすい環境を整える資材のことです。
野菜や草花を元気に育てるには、その植物に適した土作りが欠かせません。ただ肥料を与えるだけでは不十分で、土そのものが健全でなければ、やがて生育不良を起こし、最悪の場合は枯れてしまうことも…。
そこで役立つのが土壌改良材。土の質を改善し、水はけ・通気性・保水性などを調整することで、植物にとって理想的な環境を作ることができます。
植物を元気に育てるための“土のリフォーム”、それが土壌改良材の役割なのです。
どんな時に使うの?
土壌改良材を使うことで、土の状態を改善し、植物が育ちやすい環境を作ることができます。具体的には、次のような効果があります。
・水はけが良くなる(透水性の向上)
・水もちが良くなる(保水性の向上)
・土がふんわりして根が張りやすくなる(団粒構造の形成)
・硬い土を柔らかくする(土壌の膨軟化)
・肥料の効果を長持ちさせる(保肥性の向上)
つまり、水はけが悪い・乾燥しやすい・土が硬い・肥料が効きにくいといったトラブルがある場合に、土壌改良材を使うことで改善が期待できます。
「水はけが悪くて根腐れしやすい…」「すぐ乾燥してしまう…」など、土の状態に悩んでいるなら、土壌改良材を試してみましょう!
どんな種類があるの?
土壌改良材にはさまざまな種類がありますが、目的に応じて使い分けることが重要です。今回は、ハーブ栽培にも活用できる代表的な改良材を紹介します。
鉱物を高温加熱して粉砕したもの
特徴
・軽量で扱いやすい
・水はけ・水もち・通気性のバランスを整える
・無菌なので、挿し木や種まきにも適している
黒曜石を高温加熱して発泡させたもの
特徴
・水はけを良くし、通気性を改善
・粒の内部に無数の空洞があり、根に酸素を供給
・鉢底石の代わりとしても活用可能
※ハーブ栽培では、水はけを良くするために特におすすめ!
真珠岩を高温加熱して発泡させたもの
特徴
・保水性と保肥力を高める
・水分を適度に保持し、乾燥しにくい土にする
<黒曜石パーライトと真珠岩パーライトの違い>
- 黒曜石パーライト → 水はけ重視(乾燥しやすい土向け)
- 真珠岩パーライト → 水もち重視(乾燥しやすい環境向け)

黒曜石パーライトと真珠岩パーライトはどちらも通気性を良くしてくれますが、一方は水はけに効果あり、もう一方は水もちに効果ありで、水分コントロールの面では別の効果があります。
ハーブの栽培では、主に水はけを良くする黒曜石パーライトを使用することが多いです。
火山灰からできた粘土鉱物
特徴
・保肥力を向上させ、肥料の効果を持続
・有機肥料と相性が良い
・水質浄化にも使われ、水耕栽培にも活用可能

ゼオライトには大きく分けて「天然ゼオライト」「人工ゼオライト」「合成ゼオライト」という種類があります。園芸で主に使われるのは「天然ゼオライト」です。
水苔や水草が長年かけて泥炭化したもの
特徴
・保水力・保肥力を高める
・土を酸性に傾ける(特に無調整タイプ)
<注意点>
・ハーブ栽培ではあまり使用しない(アルカリ性を好むため)
・ブルーベリーやツツジなど、酸性土壌を好む植物に適している

ピートモスには「無調整」と「酸性度調整済」の2種類があります。どちらも土を酸性に傾ける性質がありますが、無調整の方が強く酸性に傾けます。
ドロマイトという鉱石を粉砕したもの
特徴
・土をアルカリ性に調整する
・水はけと通気性を改善
・ハーブ栽培に適した土づくりに欠かせない
まとめ
| 土壌改良材 | 主な効果 | ハーブ栽培でのおすすめ度 |
|---|---|---|
| バーミキュライト | 水はけ・水もち・通気性改善 | ⭐⭐⭐ |
| 黒曜石パーライト | 水はけを良くする | ⭐⭐⭐⭐ |
| 真珠岩パーライト | 水もちを良くする | ⭐⭐ |
| ゼオライト | 保肥力を高める | ⭐⭐⭐ |
| ピートモス | 土を酸性にする | ⭐(ハーブには不向き) |
| 苦土石灰 | 土をアルカリ性にする | ⭐⭐⭐⭐ |
ハーブ栽培では、黒曜石パーライトや苦土石灰を上手に活用することで、根腐れしにくく丈夫な土を作ることができます!
土壌改良材の使い方
市販の培養土は、水はけ・水もち・保肥力などのバランスが最適に調整されているため、基本的に土壌改良材を加える必要はありません。むしろ、細かい調整ができないまま改良材を追加すると、かえって土のバランスを崩してしまうことがあるので注意しましょう。

しかし、以下のようなケースでは土壌改良材を活用することで、より植物が育ちやすい環境を作ることができます。
・地植えをする場合(庭や畑の土を使う)
・鉢植えに庭や畑の土を使用する場合
・自分でオリジナルの土ブレンドを作りたい場合
ここからは、どの土壌改良材をどんな目的で、どのくらい使えばよいのかを解説します。
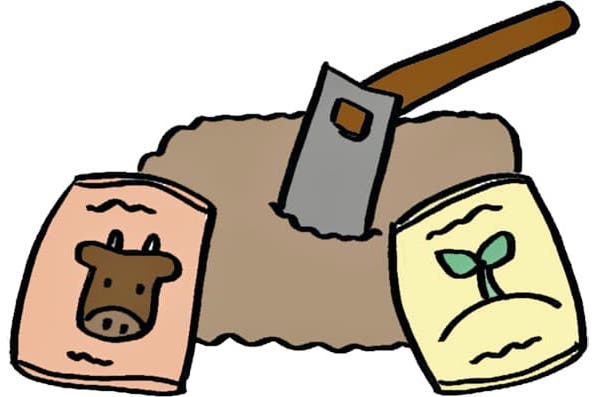
基本的には土に混ぜて使いますが、混ぜ込み直後は熱やガスを発生して植物を傷めてしまう場合がありますので植え付けの2〜3週間前には作業を済ませておきましょう。
使用量の目安は下記の表の通りです。
| 種類 | 使用目的 | 土に対しての使用量目安 |
| バーミキュライト | 水はけ、水もち、 保肥力、通気性の向上 | 5%〜10% |
| 黒曜石 パーライト | 水はけ、通気性の向上 | 10%〜20% |
| 真珠岩 パーライト | 水もち、保肥力の向上 | 10%〜20% |
| ゼオライト | 保肥力、通気性の向上 | 5%〜10% |
| ピートモス | 水もち、保肥力の向上 アルカリ土壌の矯正 | 20%〜30% |
| 苦土石灰 | 酸性土壌の矯正 | 0.5%〜1% |
※上記の使用量はあくまで目安となります。使用する土の性質や製品ごとの特徴をしっかり理解した上で使用量を決めましょう。(土壌改良材を購入した際には、必ずパッケージ裏面の説明を確認した上で使用しましょう。)
日本最大級ショッピングサイト!お買い物なら楽天市場
簡単に土壌チェックをする方法

土壌改良材を使用する前に、本当に土を改善する必要があるのかを確認することが大切です。
すでに良好な土壌なのに無理に改良すると、かえって排水性や保水性のバランスを崩し、逆効果になることもあります。
土の養分を正確に測定するには専門業者の分析が必要ですが、排水性・通気性・保水性については、ご自身で簡単にチェックする方法があります。
次の方法を試して、まずは今の土の状態を把握してみましょう!
水はけ・通気性をチェックする方法
📝 確認方法:「雨天後の土の状態を観察」
- 半日ほどで雨水が吸収された → 排水性・通気性は良好!
- 数日経っても水が土に染み込まない → 排水性・通気性が悪いので、改善が必要!
🌱 対策ポイント
水はけが悪い場合は、黒曜石パーライトやバーミキュライトを混ぜて土を軽くすると改善できます。
水もちをチェックする方法
📝 確認方法:「透明な瓶に土と水を入れて振り、しばらく放置」
- 5分程度で土と水が分離した → 砂質 or 団粒構造が良好!
- 水が濁ったまま長時間変化なし → 粘土質 or 単粒構造が悪い可能性あり!
🌱 対策ポイント
乾燥しやすい場合は、真珠岩パーライトやピートモスを混ぜると水もちを改善できます。
【送料無料】農大式簡易土壌診断キット みどりくん スターターキット
最後に
今回は、ハーブ栽培でよく使われる土壌改良材に絞ってご紹介しました。
土壌改良材には、他にも野菜農家が使用する「バーク堆肥」や「泥炭」、水稲農家が活用する「ベントナイト」など、さまざまな種類があります。しかし、大切なのは本当に改良材が必要かどうかを見極めることです。
まずは土の状態をチェックし、必要に応じて適切な改良材を選びましょう。
また、本記事で登場した水はけ・水もち・保肥力・団粒構造・単粒構造について詳しく知りたい方は、ぜひ前回の記事も参考にしてみてください。



