はじめに
「花言葉」と聞いて、皆さんはどんなイメージを思い浮かべますか?心に響くロマンチックな意味や、深い歴史を感じるエピソード……でも、実際のところ、その由来や決まりごとを知っている人は意外と少ないのではないでしょうか。
実は、花言葉の起源についてもはっきりとした答えはなく、諸説が語られています。その中でも有力なのは、17世紀のトルコで始まり、ヨーロッパを経て明治時代に日本へ伝わったという説です。そして、日本では独自の文化や風習に合わせて解釈が進化し、今日に至っています。

興味深いのは、花言葉が国や地域によって異なるだけでなく、ポジティブな意味とネガティブな意味を同時に持つこともあるという点です。例えば、「マリーゴールド」には「変わらない愛」という素敵な花言葉がある一方で、「嫉妬」という少しダークな側面も……。そのギャップが何とも不思議で魅力的ですよね。
でも、花言葉の本当の魅力は、言葉そのものに意味を求めるのではなく、自分自身がどんな思いをその言葉に重ねるかにあるのかもしれません。例えば、日々の生活の中でふとハーブに触れ、その花言葉に元気をもらう。そんな小さな瞬間が、心を豊かにしてくれるのではないでしょうか。
そこで今回は、身近な「ハーブ」をテーマに、私たちを前向きな気持ちにしてくれるポジティブな花言葉をご紹介します。ハーブティーを飲んだり、お手入れをしたりしながら花言葉に触れることで、いつの間にか心が明るくなっているかもしれません。
それでは、ハーブの花言葉が秘めた力を一緒に探ってみましょう!
ハーブの花言葉 8選
カモミール

カモミールの花言葉は【逆境下の力】です。
この花言葉には、カモミールが持つたくましい生命力がそのまま反映されています。実際に育てたことがある方ならご存知かもしれませんが、カモミールは一度花を終えた後でも、こぼれ種から翌年に新しい芽を次々と出すのです。まるで、どんな環境でも希望を見いだし、再び力強く生き抜く姿を象徴しているかのようです。
特に「ジャーマンカモミール」は一年草でありながら、その生命力は群を抜いています。枯れても種が土の中で静かに息づき、翌年には再び芽を出して花を咲かせます。秋に植えられた苗は、寒さ厳しい冬を耐え忍び、春には見事な花を咲かせる準備を整えます。
厳しい環境の中でもじっくりと力を蓄え、美しい花を咲かせるカモミール。その姿は、どんな逆境にも負けない強さと希望を私たちに教えてくれるようです。「逆境下の力」という花言葉は、まさにカモミールのたくましさそのものを表しています。
タイム

タイムの花言葉は【活力】です。
古くからハーブとして親しまれてきたタイムは、特にその高い殺菌力で知られています。民間療法や日常の暮らしの中で、健康や清潔を守るために活用されてきました。その歴史の長さが、この花言葉の由来を物語っているようです。
また、タイムの爽やかで力強い香りは、気分をリフレッシュさせる効果があるとも言われています。一息深く吸い込むだけで、心がスッキリして前向きな気持ちが湧いてくる……そんな体験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。
さらに興味深いのは、古代ギリシャでの言い伝えです。「悪いものを打ち負かす」という象徴的な意味から、タイムは戦地に向かう戦士たちに贈られる縁起物として使われていたそうです。その香りとともに、勇気や力を授けるお守りのような存在だったのかもしれません。
現代でもタイムのエネルギッシュな魅力は健在です。その力強い花言葉を思い浮かべながら、タイムの香りを楽しんでみると、きっと前向きな活力が体の中から湧いてくるはずです。
筆者おすすめの素敵なタイム「ゴールデンレモンタイム」についての記事もぜひご覧ください。
ナスタチウム
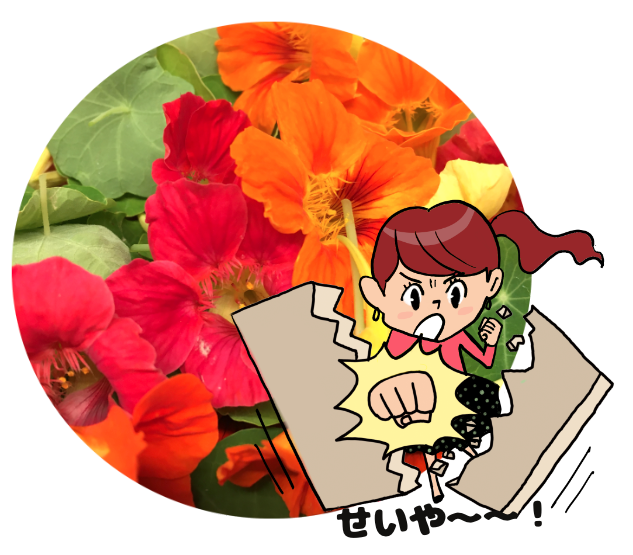
ナスタチウムの花言葉は【困難に打ち勝つ】です。
さらに「愛国心」や「勝利」といった、強さや戦いを連想させる花言葉も付けられています。その由来には、赤い花を鎧に、丸い葉を盾に見立てたという説があります。このため、少し「戦争」のイメージを思い浮かべてしまう方もいるかもしれません。しかし、ここで大切なのは、「どんな困難にも立ち向かい、乗り越える力」を象徴する花であるという点です。
ナスタチウムの明るい花色と力強い佇まいを眺めていると、「自分も頑張れる!」という気持ちが湧いてくるような不思議な魅力があります。また、ナスタチウムはエディブルフラワーとしても知られ、サラダや料理に彩りを添えるだけでなく、食べることでその象徴的な「力」を体内に取り込むこともできるかもしれません。
実際にナスタチウムを育ててみたいという方は、下記のページもあわせてご覧ください。
オレガノ

オレガノの花言葉は【あなたの苦痛を除きます】です。
料理のスパイスとして馴染み深いオレガノは、実はタイムと同じく優れた殺菌力・抗菌力を持つハーブです。そのため、古くから消化器系や呼吸器系の不調を和らげるハーブ療法に用いられてきました。また、「ストレスの緩和」にも効果があるとされており、疲れた心身を優しく癒す存在として親しまれています。
こうした癒しの力が、この花言葉に込められた背景なのでしょう。また、オレガノには「財産」や「富」といった花言葉もあります。これは、健康や豊かさを象徴するハーブとしての役割を表しているのかもしれません。
オレガノを育ててみたい方は下記の記事をご参照ください。
フェンネル

フェンネルの花言葉は【強い精神力】です。
その甘くスパイシーな独特の香りで、料理の香り付けやサラダのアクセントとして広く知られるフェンネル。実はこのハーブ、史上最古の栽培作物の一つとも言われ、古代から人々に愛されてきた歴史を持っています。
古代ギリシャやローマでは、フェンネルは「勇気」と「力」を象徴する植物として、戦士たちの食事や儀式に用いられました。また、薬用ハーブとして消化促進や健康維持に役立てられるなど、その活用の幅広さも特筆すべき点です。
長い歴史の中で途切れることなく愛され続けてきたフェンネル。絶え間ない人気とその香りが持つ力強さは、「強い精神力」という花言葉にふさわしいと言えるでしょう。
フェンネルの特徴や育ててみたい方は下記のページをご参照ください。
アロエ

アロエの花言葉は【健康】です。
日本では「医者いらず」として昔から親しまれているアロエ。その名の通り、火傷や切り傷に塗ることで肌を癒したり、胃腸の調子を整えるために食べたりと、さまざまな場面でその効果を発揮してきました。近年では、飲み物やデザートの材料としての利用はもちろん、美容関連の商品にも多く使われるようになり、ますます私たちの生活に欠かせない存在となっています。
また、アロエには【万能】という花言葉もあります。その理由は、薬用としてだけでなく、食用やスキンケアなど幅広い分野で活躍するその特性にあるのでしょう。ひとつの植物でこんなにも多くの恩恵を受けられるのは、まさに「健康」や「万能」という花言葉がふさわしいハーブと言えます。
シソ

シソの花言葉は【力が蘇る】です。
「和ハーブ」として親しまれるシソは、古くから日本で食用や薬用に利用されてきた植物です。実はその起源をたどると、ヒマラヤから中国を経て日本に渡ってきたと言われています。今では薬味として家庭の食卓に欠かせない存在となり、特に夏にはその効果が大活躍。シソには食欲を増進させたり、消化を助けたりする作用があり、暑さで弱った体を元気にしてくれます。
漢字で「紫蘇」と書かれるシソ。その「蘇」という字には「蘇る」という意味が込められています。この由来は、中国の古い故事にあります。食中毒で瀕死状態だった若者にシソを与えたところ、見事に回復したという伝説から、弱った力を復活させる植物として知られるようになったのです。
こうした背景を知ると、「力が蘇る」という花言葉がシソにぴったりであることがよくわかりますね。
月桂樹

月桂樹の花言葉は【栄光】です。
「ローレル」や「ローリエ」とも呼ばれるこのハーブは、地中海沿岸を原産とし、私たちの生活に馴染み深い存在です。その清涼感のある葉は、煮込み料理の香り付けや臭い消しとして広く利用されるだけでなく、古代から「栄光」と「勝利」を象徴する神聖な植物として崇拝されてきました。
特に古代ギリシャ時代、月桂樹の葉で作られた「月桂冠」は、競技の勝者や詩人、学者などに贈られる栄誉の証でした。月桂冠を受けるということは、人生の勝利者として認められることを意味していたのです。この背景が、月桂樹に「栄光」という花言葉が付けられた理由なのでしょう。
さらに、ヨーロッパの一部では月桂樹を玄関先に植えると魔除けになると信じられていたほど、その力強いエネルギーが人々に広く認識されていました。逆境や困難に打ち勝つ象徴として、今もその存在感を放っています。
月桂樹は庭木にもおすすめです。下記の記事で育て方などを解説しています。
薬膳・アーユルヴェーダ・スパイスの資格を取得取得講座
最後に
私たちの生活は、日々さまざまな変化に直面しています。その中で、植物が持つ自然の力は、いつでも静かに私たちを支え、心に活力を与えてくれる存在です。
例えば、窓辺に置かれた鉢植えの草花。その花に「希望」という花言葉がついていたら、どんな気持ちになるでしょうか?また、もし「失望」という花言葉も同じ花についていたとしたら、あなたはどちらの意味を受け入れるでしょうか。
花言葉は、一つの言葉に込められたメッセージを通して、私たちに物事の捉え方を問いかけてくれます。それは植物を育てる時間そのものが、私たちの心と向き合い、癒し、成長させてくれる大切なひとときになるということではないでしょうか。
植物と触れ合い、育てることで、私たちは自然から多くを学び、力をもらうことができます。この小さなつながりこそが、これからの時代に私たちにとって大きな支えとなり、新たな希望を生み出すきっかけになるような気がしています。
音声解説のご紹介(YouTubeチャンネル)
この記事の内容は、当サイトの公式YouTubeチェンネルにて、音声コンテンツとして誰でも気軽に楽しんでいただくことができます。ぜひチャンネル登録の上、ご視聴ください。
・公式YouTubeチャンネル →「3 Minutes Gardening」はこちらから
・本記事の音声版 →元気と活力をくれる!ハーブの花言葉集|音声のみ【Botanic Note】








