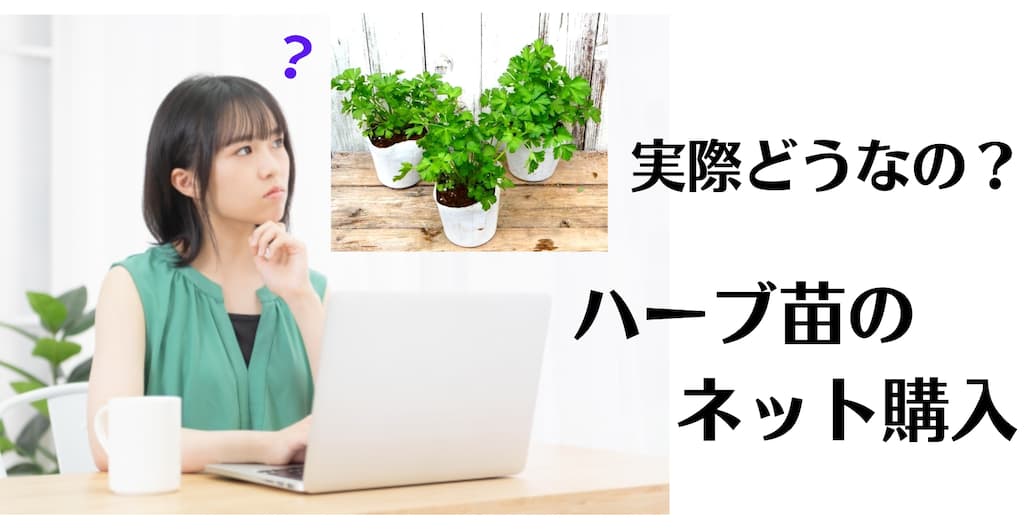はじめに
スーパーや直売所、道の駅で目にする「無農薬」や「特別栽培」という表示。健康や安全を意識する方にとって、こうしたキーワードは魅力的に映りますよね。特にオーガニック志向が高まる昨今では、「無農薬だから安心」「特別栽培なら安全」と感じて手に取る方も増えています。

でも、その「無農薬」や「特別栽培」という言葉、本当に正しく理解できていますか? 表示されているからといって、必ずしもすべてがイメージ通りとは限らないのです。
この記事では、「無農薬」と「特別栽培」の本当の意味や、現在の表示に至った背景をわかりやすく解説します。知識があれば、お買い物の際により納得して選べるようになるはずです。次のお買い物が少し賢く、楽しくなるかもしれませんよ!
直売所や道の駅で販売されている農産物や加工品にはよく「無農薬」や「特別栽培」といった表現が使われています。
無農薬と特別栽培の違い
はじめにお伝えしておくと、「無農薬」と「特別栽培」はその名前から受ける印象とは異なり、全く異なる意味を持っています。
一見すると、
- 無農薬 = 農薬を一切使わずに栽培されたもの
- 特別栽培 = 手間ひまをかけて特別な方法で育てられたもの
といったイメージを抱くかもしれません。しかし実際には、これらの表示には曖昧さが残り、消費者が混同しやすい状況にあります。そうした誤解を防ぐために、現在ではそれぞれの表示に関する明確なガイドラインが設けられているのです。
次のセクションで、その違いを詳しく見ていきましょう。
無農薬とは?
「無農薬」とは、農薬を一切使用していないことを示す言葉です。 しかし、最近では店頭や商品のラベルで「無農薬」という表記を目にする機会が少なくなってきたと感じていませんか? 実は、現在「無農薬」と表示することは 法律上禁止されているのです。
無農薬という表示が禁止された理由
日常的に使われている「無農薬」という言葉ですが、農林水産省が定めた「特別栽培農産物に関わる表示ガイドライン」により、現在では商品に「無農薬」と記載することはできません。このガイドラインが施行されたのは 2004年 と、すでに長い年月が経過していますが、今でもこの事実に驚く方は少なくありません。
では、なぜこのような規制が設けられたのでしょうか?
無農薬表示が誤解を招く理由
一番の理由は、 消費者が誤解をしやすい という問題です。

たとえば、ある農家が自分の畑で完全に農薬を使わずに野菜を育てていたとしましょう。しかし、その隣の畑では大量の農薬が使用されていたとしたらどうなるでしょうか? 風や虫を通じて農薬が飛散する可能性があり、農薬を使っていない畑でも、完全に「農薬ゼロ」と言い切れる保証はありません。
以前は、農家が自己申告で「無農薬」とラベルをつけて販売することができましたが、 厳密な基準がないことが問題視され、誤解を招く恐れがあるとしてガイドラインが設けられたのです。
無農薬の表記が残っている理由
「それなのに、直売所やインターネットで『無農薬』と書かれている商品を見かけるのはなぜ?」と疑問に思う方もいるかもしれません。その答えは、 ガイドラインに罰則がないためです。
特別栽培とは?
特別栽培の定義
無農薬として販売されていた作物は、現在「特別栽培農産物」というカテゴリーで流通しています。では、その「特別栽培農産物」とは具体的にどのような基準なのでしょうか?
農林水産省の「特別栽培農産物に関わる表示ガイドライン」では、次のように定義されています。
「特別栽培農産物」とは、地域の慣行レベルに対して、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物を指します。
(※引用元:農林水産省「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」より)
この説明だけでは少し分かりづらいかもしれませんので、シンプルに分解して説明します。
特別栽培を簡単にいうと
- 農薬の使用量が、地域で一般的に使われている量の半分以下で育てられた農産物
(農薬を一切使用していない場合も含みます) - 化学肥料の窒素成分量が、地域の基準の半分以下で育てられた農産物
(化学肥料を一切使用していない場合も含みます)
つまり、「特別栽培農産物」には 農薬や化学肥料を全く使わない農産物 も含まれますが、 一般的な農法より使用量を抑えたもの も同じく「特別栽培」として扱われるのです。
特別栽培=無農薬とは限らない
ここが消費者にとって混乱しやすいポイントです。農薬や化学肥料を少しでも使用していれば、「無農薬」とは言えませんが、基準値内であれば「特別栽培」として表示されるのです。
「それでは無農薬と何が違うのか?」と感じる方もいるかもしれませんが、この点については次のセクションで解説する 具体的な表示ルールがカギとなります。
特別栽培品の表示例
特別栽培農産物のパッケージには、農薬や化学肥料の使用状況が具体的に記載されています。以下に、主な表示例を紹介します。
- 農薬:栽培期間中不使用
- 節減対象農薬:栽培期間中不使用
- 化学肥料(窒素成分):栽培期間中不使用
これらの表示があれば、栽培中に農薬や化学肥料が一切使用されていないことを意味します。
- 節減対象農薬:当地比 ○割減
- 節減対象農薬:○○地域比 ○割減
- 化学肥料(窒素成分):当地比 ○割減
- 化学肥料(窒素成分):○○地域比 ○割減
「○割減」という表記は、各地域で一般的に使用されている基準と比較して、農薬や化学肥料の使用がどれだけ削減されているかを示しています。
「無農薬」から「具体的な表示」へ
以前は「無農薬」というシンプルな表現で消費者に伝えられていましたが、その反面、定義が曖昧で誤解を生むことがありました。現在は「特別栽培」という言葉に置き換わり、具体的な使用状況を細かく表示することで、より正確な情報が消費者に伝わるようになっています。
無農薬の農産物を選びたい場合は?
もし、農薬や化学肥料を一切使っていない農産物を購入したい場合は、「農薬:栽培期間中不使用」 や 「化学肥料(窒素成分):栽培期間中不使用」 と表示された商品を選びましょう。このような表示があれば、安心して購入することができます。
全国の美味しい特別栽培米はこちらからチェック!
最後に
私たちの生活の中には、イメージが先行して具体的な意味が曖昧なまま使われている言葉が意外と多く存在します。
今回取り上げた「無農薬」や「特別栽培」だけでなく、「オーガニック」や「有機」といった言葉もその一例です。何となく安心・安全と捉えがちですが、それぞれに明確な基準があることを理解しておくと、より納得した選択ができるようになります。
さらに詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひご覧ください。