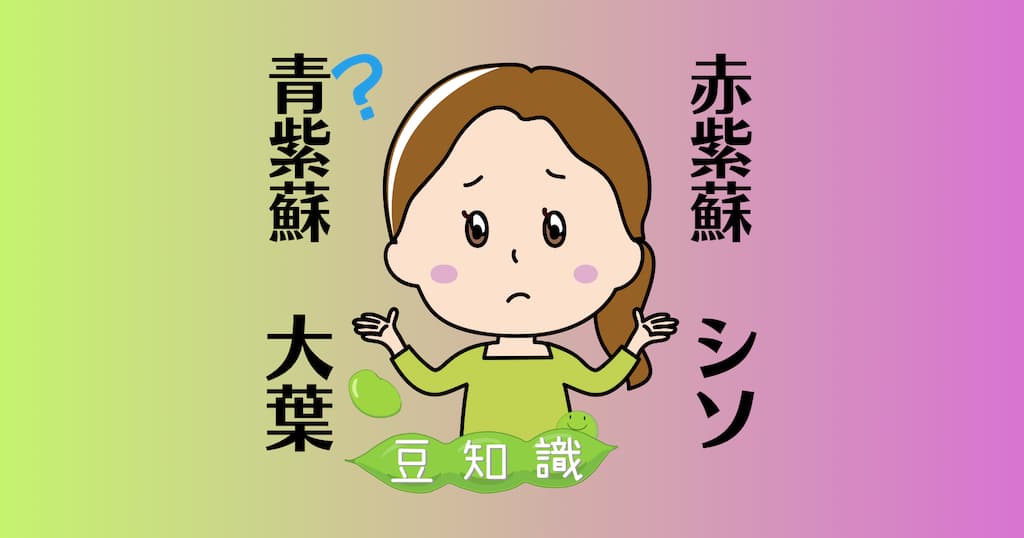はじめに

日本人の食生活に欠かせない存在の「シソ」は、誰もが口にしたことがある身近な野菜でありハーブです。
清々しい香りとほのかな苦味で、様々な料理の薬味として古くから用いられており、魚の臭み消しに使われたり、そのまま天ぷらにして食べたり、梅干しを漬けるときに使われたり、その用途は多岐にわたります。

しかし、紫蘇は、時と場合によって「シソ」と呼ばれたり「大葉」と呼ばれたり、更に「赤紫蘇(あかじそ)」「青紫蘇(青じそ)」といった色の違いもあるので、一体どういうことだろう…と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
今回はそんな疑問を解消するために、それぞれの違いについて解説していきたいと思います。
シソの品種について
まず最初にご説明しておかなくてはならないのが、シソと言っても様々な品種があるということです。
皆さん、同じシソでも、葉が縮れているもの、または逆に縮れのない平らな葉を見たことありませんか?
どれも「シソ」であることに変わりはありませんが、大別すると下記のような種類に分けられます。
赤紫蘇

【特徴】
▶︎葉は平らで、色は赤紫。
▶︎6〜7月頃に流通する。
▶︎アントシアニンを豊富に含む。
青紫蘇

【特徴】
▶︎葉は平らで、色は緑。
▶︎ハウス栽培であれば年中流通する。
▶︎赤紫蘇よりもβカロテンが多く含まれる。
ちりめん赤紫蘇

【特徴】
▶︎葉に縮れがあり、色は赤紫。
▶︎6〜7月頃に流通する。
▶︎アントシアニンを豊富に含む。
ちりめん青紫蘇

【特徴】
▶︎葉に縮れがあり、色は緑。
▶︎ハウス栽培であれば年中流通する。
▶︎赤紫蘇よりもβカロテンが多く含まれる。


上記の品種の他にも、葉の表が緑色で裏が紫色の品種「片面紫蘇(カタメンジソ)」や「斑紫蘇(マダラジソ)」と呼ばれる栽培品種もあります。
肉厚で香りが強いのが特徴で、生食にはあまり向いておらず、ふりかけや飲料などの加工に用いられます。
上記の通り、品種によって、基本的には色と縮れの有無、用途に違いがあります。
赤紫蘇と青紫蘇の違いとは?
シソは色と用途で大別すると、赤紫色の「赤紫蘇(あかじそ)」と緑色の「青紫蘇(あおじそ)」に分けられます。
一般的には「シソ」といえば赤紫蘇をさすことが多く、青紫蘇は赤紫蘇の変種とされています。
しかし、どちらも「シソ」と呼んでも間違いではありません。
色以外にも、下記のような違いがあります。
成分の違い
2つのシソと比較すると、赤紫蘇には「アントシアニン」が多く含まれ、青紫蘇には「βカロテン」が多く含まれています。
赤紫蘇が赤いのは、ポリフェノールの一種「アントシアニン」という成分によるものです。アントシアニンはブルーベリーやブドウにも含まれている天然の色素です。βカロテンは緑黄色野菜のパセリやカボチャ、ブロッコリーなどに含まれている栄養素です。
(βカロテン自体は赤と青どちらのシソにも豊富に含まれていますが、青紫蘇の方がより多くの量を含んでいます。)
用途の違い


赤紫蘇は、梅干しや漬物の色付け、ふりかけ、紫蘇ジュースなどに使われ、色合いを活かした加工品に対して天然着色料として、もしくは風味を活かす素材として主に活用されます。


青紫蘇は、薬味や天ぷら、刺身のつまや添え物に使われ、香味野菜としての利用価値があります。
平葉と縮緬とは?
シソには、葉が平らな品種(平葉)と、葉が縮れている品種(ちりめん)があります。
形以外の違いはほとんどありませんが、用途によってそれぞれニーズが異なります。
青紫蘇を例にしますと、
天ぷらにする時は平らな葉の方が扱いやすいですし、薬味にするなら平らな葉でも縮れた葉でも問題なく使えます。

栽培のお話になりますが、ちりめん品種は葉が縮むため、平葉よりも虫が葉に隠れやすく、害虫の被害にあいやすいと言われます。
また、青紫蘇の平葉が市場での一般需要も高いことから、栽培されている品種としては青紫蘇が最も多いとされています。
シソと大葉の違いとは?
皆さんは「シソ」と「大葉」の違いをご存知でしょうか?

結論から言いますと、大葉は青紫蘇の葉の呼び方の一つです。
従って、シソの一種ではあるものの、シソそのものをさす言葉ではありません。
現在は、野菜として流通する青紫蘇の葉を「大葉」と呼ぶのが一般的で、元々は静岡の生産組合が「大葉」と呼んで出荷したのが始まりとされています。
最後に
今回は、私たちの普段の食生活に身近な存在「シソ」について、知っていそうで知らない品種や呼び方の違いについて解説いたしました。
本記事を参考に、普段疑問に思っていることが少しでも解消されたのであれば嬉しい限りです。
シソの他にも、私たちの身近には似て非なる植物や、混同しやすい植物がたくさん存在します。ご興味ある方は、下記の記事もあわせてご覧ください。
音声解説のご紹介(YouTubeチャンネル)
この記事の内容は、当サイトの公式YouTubeチェンネルにて、音声コンテンツとして誰でも気軽に楽しんでいただくことができます。ぜひチャンネル登録の上、ご視聴ください。
・公式YouTubeチャンネル →「3 Minutes Gardening」はこちらから
・本記事の音声版 →大葉と青紫蘇、赤紫蘇の違いをわかりやすく解説!|音声のみ【Botanic Note】